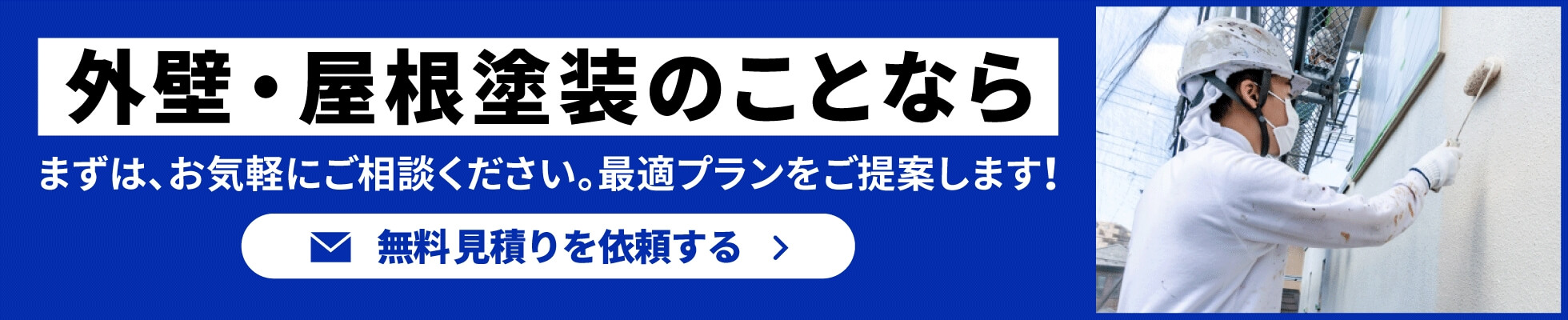コラム
建材
窯業系サイディングの特徴とは?メリット・デメリット、メンテナンス方法などを詳しく解説
2022.06.11
CONTENTS
窯業系サイディングは、日本の住宅で最も多く用いられている外壁材です。
しかし、
「自宅に窯業系サイディングを採用しているものの、メンテナンス方法がわからない」
「他の外壁材との違いは何?」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、窯業系サイディングの特徴やメリット・デメリット、どのようなメンテナンスが必要かなどを解説します。
窯業系サイディングの特徴

窯業系サイディングとは外壁材の一つであり、セメントに木材繊維などを混ぜ、板状に加工して製造されます。製造過程において、窯の中で高温処理されることから、「窯業系サイディング」という名前が付けられています。
レンガやタイル、ガルバリウム鋼板などの外壁材と比較して、施工費用を抑えやすいうえに、デザインやカラーバリエーションが豊富であることなどが人気の理由の一つです。
実際に日本サッシ教会『2022年3月版 住宅用建材使用状況調査』の調査結果によると、戸建ての外壁材の採用率は「窯業系サイディング」が76.8%、次いで「モルタル」が7.6%となっており、サイディング合計では89.1%の圧倒的な採用率を誇ります。
コストパフォーマンスやデザイン・カラーバリエーションの豊富さなどのバランスがよく、総合力の高い外壁材として評価されているといえるでしょう。
窯業系サイディングとほかのサイディングの違い
窯業系サイディングに使われている「サイディング」という言葉は、「サイディングボード」という単語が省略されています。こちらのサイディングボードとは、建物の外壁に貼り付けるパネル状の外壁材のことです。そして、サイディングボードと呼ばれる外壁材には、窯業系サイディングのほかに以下の3種類ありそれぞれ特徴が異なります。
・金属系サイディング
・樹脂系サイディング
・木質系サイディング
【金属系サイディング】
金属系サイディングとは、金属板(アルミニウムやガルバリウム鋼板)などを板状に加工した外壁材のことです。重量が軽いことが特徴であり、ガルバリウム鋼板は窯業系サイディングの約4分の1程度の重さしかありません。
金属の素材によりますが、ガルバリウム鋼板は耐震性や耐用年数に優れている一方、窯業系サイディングよりも単価が高い、デザインの選択肢が少ないといった違いがあります。
【樹脂系サイディング】
樹脂系サイディングは、塩化ビニール樹脂を主原料とした外壁材です。耐久性や耐用年数に優れている一方、窯業系サイディングよりもコスト面やデザイン性では劣っている傾向があります。
【木質系サイディング】
木質系サイディングは、名前の通り木材を使用している外壁材です。木材なので、水や火に弱く耐用年数は7〜10年ほどしかありません。しかし、天然素材ならではのあたたかみを感じられるでしょう。
外壁材に窯業系サイディングを採用するメリット

窯業系サイディングは主流の外壁材となっており、多くの住宅で採用されています。
では、窯業系サイディングにはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
初期費用を抑えやすい
まず、初期費用を抑えやすいことがメリットとして挙げられます。というのも、窯業系サイディングは工場での大量生産が可能であり、外壁材自体の単価が安い傾向にあるからです。さらに、軽量の薄いボードを外壁に貼り付ける簡単な工程で施工できるため、施工時の人件費も抑えられます。
素材自体の単価が安く、施工費用を抑えられることから、結果的に初期費用を抑えて採用できるのはメリットだといえるでしょう。
耐火性に優れている
耐火等級とは住宅性能表示制度で定められた、「火災時の安全」に関する指標の一つであり、1〜4までの等級の中で数字が大きくなるほど耐火性能が高いと判断されます。製品によって耐火性が異なるものの、窯業系サイディングは耐火等級3〜4を取得しているものが多く、耐火性に優れた外壁材であるといえます。なお、耐火等級4とは、「延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さが60分相当以上」という基準をクリアしている外壁材しか取得できません。
火災は自宅が出火元になるリスクに加え、近所からのもらい火によって被害を受けるリスクもあります。そのため、耐火性の高さはメリットとなるでしょう。
デザイン・カラーのバリエーションが豊富
外壁は住宅の第一印象を決める要素なので、こだわりたい方も多いでしょう。窯業系サイディングは素材自体が加工しやすいため、デザイン・カラーのバリエーションが豊富です。
レンガやタイルなどは基本のデザインはほとんど同じですが、成型性の高い窯業系サイディングなら多種多様な選択肢から自宅に採用するデザインを決められます。シンプルな単色のデザインもあれば、タイル調や石柄、木目調、和風、モダンテイストなどもあります。
さらに、カラーのバリエーションも豊富なので、理想とする住宅の外観を実現しやすいのはメリットだといえます。
施工が比較的簡単で工期が短い
窯業系サイディングは板状にカットされており、決まった大きさのボードを貼り付けていくので施工が比較的簡単であり、施工期間を短く抑えて人件費を削減できるメリットもあります。たとえば、モルタルなどの塗り壁を施工する場合、すべて現場の職人が手作業で作業を進めなければならず、施工期間も長くなりがちです。さらに、手作業の工程が多いと、仕上がりにバラつきがでやすいのも懸念点でしょう。
しかし、窯業系サイディングなら、工場で加工されたボードを貼り付ける施工方法なので、施工期間が短く、なおかつ仕上がりも均一になりやすいというメリットがあります。
外壁材に窯業系サイディングを採用するデメリット
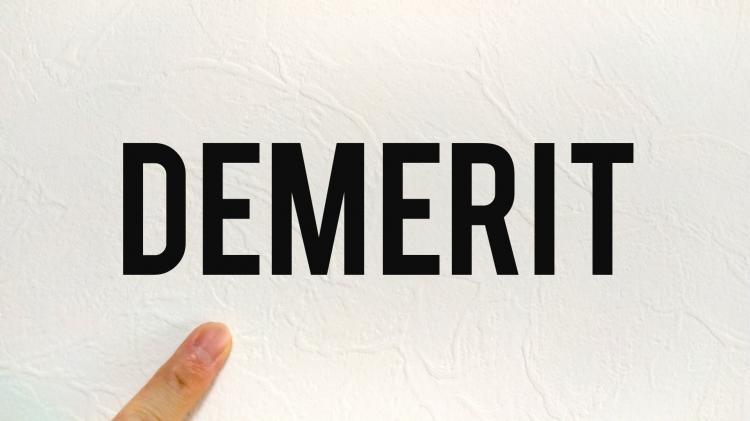
さまざまなメリットのある窯業系サイディングですが、デメリットも存在します。
では、どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
定期的なメンテナンスが必要
まず、こまめなメンテナンスが必要な点はデメリットといえるでしょう。外壁塗装の塗料の種類にもよりますが、窯業系サイディングは10年に一度を目安に塗り替えが必要だと言われています。さらに、ボードの隙間や目地を埋めているシーリングは5〜10年程度でひび割れなどの劣化が見られるため、別途シーリングのメンテナンスも必要になります。
40坪2階建ての外壁塗装を行う場合おおよそ90〜140万円となるため、メンテナンスコストがかかる点は注意しましょう。
蓄熱性がある
窯業系サイディングに使用されているセメントは、蓄熱性を持つ素材です。夏場は外壁材からの熱が室内に伝わり、室内が暑く感じられやすくなったり、冷房効率を下げたりすることがあります。
室内の暑さが気になる場合は窯業系サイディングが原因である可能性が考えられるため、外壁塗装で遮熱・断熱効果の高い塗料を採用するなどの対策が必要になるでしょう。
本物の質感には劣る
窯業系サイディングはタイル調やレンガ調、木目調などさまざまなデザイン・カラーバリエーションがある点をメリットとして挙げましたが、あくまでデザインとして再現しているため本物ではありません。最近ではデザイン技術が向上しているので本物に近い見た目の外壁材も増えていますが、やはりタイルやレンガなどの本物にしかない質感には劣ります。
とはいえ、レンガやタイルを外壁に採用すると高額になるため、本物のような質感を費用を抑えつつ採用できるのは魅力といえるでしょう。予算と質感のバランスを慎重に検討するのがおすすめです。
窯業系サイディングはどのような方におすすめ?

窯業系サイディングは住宅の外壁材として圧倒的に高いシェア率を誇っている通り、外壁材に求められるポイントをバランスよく満たしていて人気ですが、おすすめできる場合とできない場合があります。
窯業系サイディングは、外壁材に対して以下のような条件を求める人におすすめです。
・初期費用を抑えたい
・本物の質感よりも、コストとのバランスの方が大切
・採用率の高い外壁材なら安心できる
・デザインやカラーバリエーションの豊富さを重視したい
・定期的にメンテナンスが可能
コストメリットが大きいことや、定期的にメンテナンスを行って状態を維持できるという方には、窯業系サイディングがぴったりでしょう。
一方、初期費用をかけてでもメンテナンス頻度やランニングコストを抑えたい、れんがやタイルの本物の質感を求めたいという方には不向きである可能性があります。
窯業系サイディングに必要なメンテナンスと費用相場

ここでは、窯業系サイディングに必要なメンテナンスと費用相場を解説します。
コーキングの打ち替え・打ち増し<
窯業系サイディングのボードの隙間や目地を埋めているシーリングは劣化しやすい箇所の一つであり、シーリングが劣化するとそこから雨水が住宅内に侵入するリスクが高くなります。
そこで、シーリングは5〜10年に一度を目安にメンテナンスが必要であり、施工方法は「打ち替え」と「増し打ち」という二つの選択肢があります。
既存のコーキングを撤去し、新しいコーキングを打つ「打ち替え」の場合は1mあたり1,200〜1,300円程度、既存のコーキングの上から新しいコーキングを打つ「増し打ち」の場合は1mあたり900〜1,000円が相場になるでしょう。
高圧洗浄
外壁塗装を行う際、高圧洗浄という工程がセットで行われます。高圧洗浄とは、高圧洗浄機という機械を使用し、強力な水圧で外壁をクリーニングする作業のことを指します。
外壁塗装自体が劣化しておらず表面だけに汚れが生じている場合は、メンテナンスとして高圧洗浄のみが行われるケースもありますが、高圧洗浄と外壁塗装は同じタイミングで行われるのが基本です。
一般家庭にある水道の水圧は2~4㎏f/㎠程度であるのに対し、業務用の高圧洗浄機の水圧は150~200㎏f/㎠程度と非常に強い水圧であり、強力が水圧を使うことで長年外壁にこびりついた汚れを落とせます。
高圧洗浄の費用は1㎡あたり200〜300円、さらに水道代は1,000〜2,000円ほどかかります。なお、バイオ洗浄など、薬剤を使って行う場合はプラスの費用が必要です。
外壁塗装
外壁塗装は建物の外壁を塗装することであり、住まいの美観を維持するだけでなく、雨風や紫外線から守って寿命を延ばしたり、カビやコケ、ひび割れなどの劣化を補修したりする効果があります。
窯業系サイディング自体には防水性がないため、外壁塗装の効果が切れた状態では住宅内に雨水が浸透して劣化の原因になります。そのため、周辺環境や塗料の種類によりますが、10〜15年に一度の再塗装が必要です。
外壁塗装の施工期間は2週間程度、40坪2階建ての住宅ならおおよそ90〜140万円が施工費用の相場です。塗料のグレードや外壁の状態によってかかる費用が変わるため、施工費用の相場はあくまで目安として考え、詳細な金額は外壁塗装業者に見積もりを依頼しましょう。
カバー工法
外壁塗装はカビやコケなどの軽度な劣化症状を補修できますが、大きなひびが生じているなど劣化が深刻な場合は対処しきれません。
そこで、窯業系サイディングの劣化が激しい場合は、カバー工法が行われることがあります。カバー工法とは、既存の外壁材の上に新たな外壁材を重ねる方法のことです。
外壁材が二重になって構造躯体へ負荷がかかるため、重量が軽い金属系サイディングが用いられることが多い傾向にあります。
外壁塗装では対応できない深刻な劣化具合でも施工できるうえに、既存の外壁材を撤去・処分する手間が不要なので、外壁を新たに張り替えるよりも安いというバランスの良さが魅力です。
とはいえ、カバー工法は30坪の住宅でも150万円前後と高額な費用がかかるため、劣化が深刻化する前に外壁塗装でメンテナンスを行うようにしましょう。
窯業系サイディングの人気メーカーと特徴

最後に、窯業系サイディングの代表的なメーカーと、メーカーごとの特徴を見ていきましょう。
ニチハ
ニチハは愛知県名古屋市に本社がある住宅建材メーカーであり、窯業系サイディングを製造・販売する国内最大手のメーカーです。
ニチハの窯業系サイディングは、次世代インクジェット工法と呼ばれる技術により、本物の素材に近い質感や風合いを再現できることが強みです。タイル調やレンガ調、石柄などさまざまなデザイン・カラーバリエーションがあり、とくに木目調のサイディングは本物の木を思わせるようなデザインがあるので、外壁に木目を採用したい方はチェックしてみましょう。
さらに、ニチハの窯業系サイディングの一部には、プラチナコート技術が施されているので、30年以上表面状態を維持できるメンテナンスに手間がかからない製品も販売されています。
ケイミュー
ケイミューは大阪に本社がある外壁建材メーカーであり、耐候性の高い窯業系サイディングとして支持されています。
ケイミューの窯業系サイディングのシリーズの一部である「レジュールシリーズ」や「光セラシリーズ」などは、太陽の力で外壁表面に付着した汚れを分解するセルフクリーニング機能を備えています。さらに、ケイミューの窯業系サイディングは、重量が軽いため、耐震性や耐火性にも優れています。
このように、デザインやカラーだけでなく、外壁材にプラスの機能を求めたい方におすすめのメーカーです。
旭トステム
旭トステムはAGCとLIXILの外壁分野を統合して作ったメーカーであり、さまざまな技術がサイディングに生かされているのが特徴です。
とくに窯業系サイディングのラインナップである「ガーディナル」などには、色あせや変色に強い「セルフフッ素コート」機能が付いているので、長期間美しい外壁を維持できます。
さらに、サイディング同士の継ぎ目を目立ちにくくするシーリングレス工法もあり、見た目の問題から窯業系サイディングの採用を悩んでいた方にもおすすめです。
まとめ
今回は、窯業系サイディングの特徴やメリット・デメリット、メンテナンス方法などを解説しました。
窯業系サイディングは、日本の戸建てにおいて高いシェア率を誇り、多くの住宅で採用されています。
素材や施工費用が安いため初期費用を抑えて導入できることや、デザイン・カラーバリエーションが豊富であることなどがメリットである一方、外壁塗装などのメンテナンスが必要であることや、蓄熱性があることなどがデメリットとして挙げられます。
窯業系サイディングはデメリットがあるものの、外壁材に求められる要素をバランスよく満たしているため多くの住宅で採用されているのは間違いありません。
ぜひ今回の記事を参考に、納得できる外壁を見つけてみてください。
窯業系サイディングの人気メーカーと特徴

まとめ
関連コラム