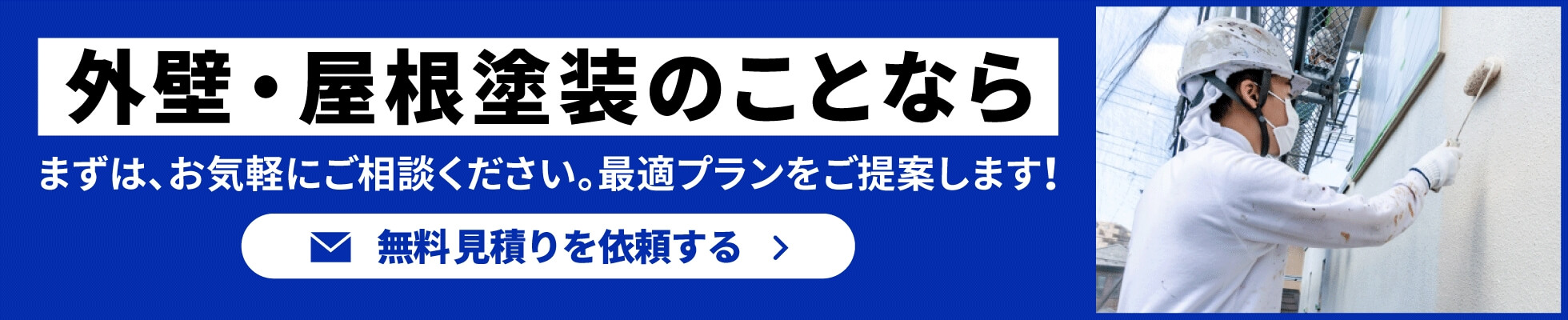コラム
外壁
外壁塗装の剥がれとは?原因や補修にかかる費用相場などを解説
2023.05.13
「外壁塗装が剥がれてきたけれど、このままで大丈夫なのかな」
「前回の外壁塗装から数年しか経っていないのに、外壁塗装が剥がれてしまった……」
など、外壁塗装の剥がれについて悩んでいる方も多いでしょう。
外壁の剥がれは見た目が悪いだけでなく、外壁塗装の効果を失っている状態であることから、放置していると住宅自体にダメージを与えてしまいます。
そこで今回は、外壁塗装が剥がれる原因を解説したうえで、対処法や補修費用の相場などを解説します。

外壁塗装が剥がれる原因は、「施工不良」または「経年劣化」の二つが考えられます。
ただし、ひとえに施工不良といってもパターンがあります。では、外壁塗装が剥がれる原因を詳しく見ていきましょう。
【塗料の耐用年数の目安】
たとえば、耐用年数15年以上が期待できるフッ素塗料で施工したにもかかわらず、経った数年で外壁塗装が剥がれたら、経年劣化ではなく施工不良が疑われるでしょう。
では、どのような施工不良が原因で外壁塗装が剥がれるのか、詳しく見ていきましょう。
下地処理とは、外壁塗装の持ちをよくするために欠かせない工程であり、主な作業内容は以下のとおりです。
【外壁塗装の下地処理の主な内容】
・ケレン作業:古い塗料を除去したり、サビや汚れを除去する作業のこと
・目荒らし:塗料の密着性を高めるために、外壁をざらつかせる作業のこと
・洗浄:塗料の密着性を高めるために、高圧洗浄で油分やホコリなどの汚れを除去すること
以上のような作業を下地処理と言います。こちらの工程が適切に行われておらず、古い塗料が残ったまま新しい塗料を塗ったり、目荒らしが不十分な状態で塗料を塗布したりすると、下地と塗料が密着せず、短期間で外壁塗装が剥がれます。
しかし、下地処理が不十分であっても、施工完了後すぐの段階ではきれいに仕上がっているように見えるのが注意点です。一見美しく仕上がっているように見えても、下地処理が不適切であったことで外壁塗装が剥がれてくる可能性があるため、定期的に外壁の状態をチェックしてください。
また、外壁塗装で使用される塗料は、乾燥時間や塗布すべき量をメーカーが定めており、それに従って塗装工程が進められます。ただし、雨の日や気温が低い日など、塗料が乾燥しにくい気候条件のときは、通常よりも長い乾燥時間が取られることもあります。
しかし、乾燥時間が守られずに重ね塗りが行われると、塗膜が形成されていないまま新しい塗料が塗布される状態となり、結果的に施工不良となるのです。
また、塗布すべき量が守られず、塗料が少なすぎたり、多すぎたりしても、塗膜がうまく形成されないことで施工不良による剥がれなどの症状が出ます。
そのため、塗料メーカーは、塗料の種類ごとに目安となる乾燥時間を定めています。ただし塗料メーカーの定める乾燥時間はあくまで目安であり、気候条件によっては規定の乾燥時間よりも長くなることもあります。
しかし、施工期間を短縮したい、工期を延長できないなどの理由で、塗料の乾燥が不十分なまま塗装工程を進めるような悪質な業者もゼロではありません。
塗膜が形成されないまま塗装が行われると、施工後はきれいに見えても、短期間で外壁塗装が剥がれる原因となります。
しかし、下塗材といってもさまざまな種類があり、外壁材や中塗り・上塗りで使用する塗料との相性が仕上がりに影響します。また、既存の下地の状態に応じて、下塗材を厚めに塗るなど、適切な使い方も求められます。
そのため、下塗材選びや使い方が適切でなければ、塗料の密着度が低下して施工不良につながるのです。下塗材の選定や使い方による施工不良は、業者の知識・技術不足が原因であるため、施工実績が豊富な業者に依頼することが対策につながるでしょう。
先に解説したとおり、外壁塗装には耐用年数があります。耐用年数はあくまで目安ですが、寿命を迎えた外壁塗装は剥がれなどの劣化症状が出始めます。
【塗料の耐用年数の目安】
外壁塗装の役割は、住宅の美観を整えることに加え、外壁材を塗膜で覆って、雨や風、紫外線などの外的要因から守ることです。しかし、常に屋外で外的要因にさらされていることから、少しずつ経年劣化が進み、耐用年数を目安に寿命を迎えることが多いのです。
たとえば、前回シリコン塗料で外壁塗装を行い、10年以上が経過して外壁塗装の剥がれが見つかったら、経年劣化が原因だと考えられるでしょう。

外壁塗装の剥がれを放置しても、自然に状態がよくなることはありません。むしろ、症状が進行する、より深刻なトラブルに発展するなどのリスクがあります。
では、外壁塗装の剥がれを放置すると、具体的にどのようなことが起こるのか見ていきましょう。
雨漏りが発生すると、住宅の中に雨水が浸透してきたり、構造躯体を腐敗させたりするでしょう。さらに、外壁塗装の剥がれにプラスして雨漏りの補修費用がかかる、カビやシロアリの発生につながる、漏電による火災のリスクが高まるなど、被害がどんどん拡大していきます。
しかし、外壁塗装の剝がれを放置すると、雨漏りやシロアリの発生などの二次被害につながり、必要以上に建物の劣化を早めてしまうリスクがあります。
建物の劣化が進むと、快適な住環境を維持できなくなるうえに、高額な修繕費がかかる可能性が高まります。

外壁塗装の剝がれを見つけたら、早めに対処することが大切です。
ここでは、外壁塗装が剥がれたときに施主がするべき対処法を紹介します。
その場合、保証期間内であれば、無償で塗装業者に補修してもらえる可能性があります。まずは以下の3つの書類を確認しましょう。
・見積書
・工事契約書
・保証書
外壁塗装の見積書や契約書には、どのような塗料・工程で工事を進めたのかが記載されています。外壁塗装の施工段階で、塗料の選定ミスや作業内容に不備がなかったかを確認するのに役立ちます。
そして、見積書と契約書を確認したら、保証書では以下の内容をチェックしてください。
・保証範囲
・保証期間
・保証内容
すぐに施工業者に問い合わせる前に、書類を確認して保証対象となるのかを施主自身がチェックしておくことで、スムーズに依頼できます。
保証対象の場合、前回塗装を依頼した業者に施工するのが一般的です。しかし、保証対象外であった場合は、前回とは異なる業者に依頼する方法もあります。
なお、外壁塗装の剥がれの補修を進めるときは、以下のポイントを確認するようにしてください。
・工程表を確認する
・工事の様子をチェックする
工程表を確認することで、塗料の乾燥時間が確保されていない、三度塗りになっていない、下地処理の工程が省略されているなど、施工不良につながりやすいポイントを見つけられます。
また、可能な限り工事に立ち会い、施工の様子を写真に残しておくこともポイントです。現場の緊張感が上がり、手抜き工事を防止できます。

最後に、外壁塗装の剥がれの補修を業者に依頼したときの費用相場を見ていきましょう。
外壁塗装の剥がれが見つかったときは、部分補修ではなく、外壁塗装による全面的な補修が行われるのが一般的です。
なお、一般的な30坪2階建ての戸建てで必要な外壁塗装の費用相場は90〜140万円が中心の価格帯です。
ただし、外壁の状態や家の形状、使用する塗料などでも金額が変わります。そのため、実際にいくらかかるのかについては、業者から見積もりを取るようにしてください。

今回は、外壁塗装の剥がれについて解説しました。
外壁塗装が剥がれる原因は「施工不良」と「経年劣化」が考えられます。
外壁塗装の耐用年数に対して、明らかに短いタイミングで外壁塗装の剥がれが発生したら、施工不良の可能性が高いといえるでしょう。施工不良で外壁塗装の剝がれが発生した場合、保証範囲内であれば無償で補修してもらえます。
ただし、保証範囲外であったとしても、外壁塗装の剝がれを放置すると雨漏りなどのリスクがあるため、早めに補修することをおすすめします。
外壁塗装の剝がれが見つかったときは、ぜひ今回の記事を参考に補習を進めてみてください。
「前回の外壁塗装から数年しか経っていないのに、外壁塗装が剥がれてしまった……」
など、外壁塗装の剥がれについて悩んでいる方も多いでしょう。
外壁の剥がれは見た目が悪いだけでなく、外壁塗装の効果を失っている状態であることから、放置していると住宅自体にダメージを与えてしまいます。
そこで今回は、外壁塗装が剥がれる原因を解説したうえで、対処法や補修費用の相場などを解説します。
外壁塗装が剥がれる原因

外壁塗装が剥がれる原因は、「施工不良」または「経年劣化」の二つが考えられます。
ただし、ひとえに施工不良といってもパターンがあります。では、外壁塗装が剥がれる原因を詳しく見ていきましょう。
施工不良
外壁塗装で使用する塗料には耐用年数が決まっています。きちんと施工されていれば、耐用年数程度は外壁塗装の状態を維持できるため、耐用年数よりも早く外壁塗装が剥がれた場合は、施工不良が考えられます。【塗料の耐用年数の目安】
| 塗料の種類 | 耐用年数 |
| アクリル塗料 | 3〜5年 |
| ウレタン塗料 | 5〜8年 |
| シリコン塗料 | 8〜12年 |
| フッ素塗料 | 15〜18年 |
| 無機塗料 | 20〜25年 |
たとえば、耐用年数15年以上が期待できるフッ素塗料で施工したにもかかわらず、経った数年で外壁塗装が剥がれたら、経年劣化ではなく施工不良が疑われるでしょう。
では、どのような施工不良が原因で外壁塗装が剥がれるのか、詳しく見ていきましょう。
下地処理が不十分であった
外壁塗装の塗装工程に入る前に行われる下地処理が不十分であった場合、外壁塗装の剥がれの原因となります。下地処理とは、外壁塗装の持ちをよくするために欠かせない工程であり、主な作業内容は以下のとおりです。
【外壁塗装の下地処理の主な内容】
・ケレン作業:古い塗料を除去したり、サビや汚れを除去する作業のこと
・目荒らし:塗料の密着性を高めるために、外壁をざらつかせる作業のこと
・洗浄:塗料の密着性を高めるために、高圧洗浄で油分やホコリなどの汚れを除去すること
以上のような作業を下地処理と言います。こちらの工程が適切に行われておらず、古い塗料が残ったまま新しい塗料を塗ったり、目荒らしが不十分な状態で塗料を塗布したりすると、下地と塗料が密着せず、短期間で外壁塗装が剥がれます。
しかし、下地処理が不十分であっても、施工完了後すぐの段階ではきれいに仕上がっているように見えるのが注意点です。一見美しく仕上がっているように見えても、下地処理が不適切であったことで外壁塗装が剥がれてくる可能性があるため、定期的に外壁の状態をチェックしてください。
塗料の使い方や施工方法が守られていない
外壁塗装の塗装工程は下塗り・中塗り・上塗りの3回の塗装工程で行われるのが基本です。また、外壁塗装で使用される塗料は、乾燥時間や塗布すべき量をメーカーが定めており、それに従って塗装工程が進められます。ただし、雨の日や気温が低い日など、塗料が乾燥しにくい気候条件のときは、通常よりも長い乾燥時間が取られることもあります。
しかし、乾燥時間が守られずに重ね塗りが行われると、塗膜が形成されていないまま新しい塗料が塗布される状態となり、結果的に施工不良となるのです。
また、塗布すべき量が守られず、塗料が少なすぎたり、多すぎたりしても、塗膜がうまく形成されないことで施工不良による剥がれなどの症状が出ます。
塗料が乾燥していないまま工事が進められた
外壁塗装の塗装工程は3回あり、重ね塗りする際に、先に塗布した塗料が十分に乾燥してから工程を進めるのが基本です。塗料が乾燥することで塗膜が形成され、紫外線や熱、雨などの外的要因から外壁材を保護できるようになります。そのため、塗料メーカーは、塗料の種類ごとに目安となる乾燥時間を定めています。ただし塗料メーカーの定める乾燥時間はあくまで目安であり、気候条件によっては規定の乾燥時間よりも長くなることもあります。
しかし、施工期間を短縮したい、工期を延長できないなどの理由で、塗料の乾燥が不十分なまま塗装工程を進めるような悪質な業者もゼロではありません。
塗膜が形成されないまま塗装が行われると、施工後はきれいに見えても、短期間で外壁塗装が剥がれる原因となります。
下塗材の選択や使い方が間違えている
外壁塗装の塗装工程のうち、下塗りの工程ではフィラー、シーラーと呼ばれる下塗材が使用されます。しかし、下塗材といってもさまざまな種類があり、外壁材や中塗り・上塗りで使用する塗料との相性が仕上がりに影響します。また、既存の下地の状態に応じて、下塗材を厚めに塗るなど、適切な使い方も求められます。
そのため、下塗材選びや使い方が適切でなければ、塗料の密着度が低下して施工不良につながるのです。下塗材の選定や使い方による施工不良は、業者の知識・技術不足が原因であるため、施工実績が豊富な業者に依頼することが対策につながるでしょう。
経年劣化
施工不良のほか、経年劣化が原因で外壁塗装が剥がれることもあります。先に解説したとおり、外壁塗装には耐用年数があります。耐用年数はあくまで目安ですが、寿命を迎えた外壁塗装は剥がれなどの劣化症状が出始めます。
【塗料の耐用年数の目安】
| 塗料の種類 | 耐用年数 |
| アクリル塗料 | 3〜5年 |
| ウレタン塗料 | 5〜8年 |
| シリコン塗料 | 8〜12年 |
| フッ素塗料 | 15〜18年 |
| 無機塗料 | 20〜25年 |
外壁塗装の役割は、住宅の美観を整えることに加え、外壁材を塗膜で覆って、雨や風、紫外線などの外的要因から守ることです。しかし、常に屋外で外的要因にさらされていることから、少しずつ経年劣化が進み、耐用年数を目安に寿命を迎えることが多いのです。
たとえば、前回シリコン塗料で外壁塗装を行い、10年以上が経過して外壁塗装の剥がれが見つかったら、経年劣化が原因だと考えられるでしょう。
外壁塗装の剥がれを放置するとどうなる?

外壁塗装の剥がれを放置しても、自然に状態がよくなることはありません。むしろ、症状が進行する、より深刻なトラブルに発展するなどのリスクがあります。
では、外壁塗装の剥がれを放置すると、具体的にどのようなことが起こるのか見ていきましょう。
雨漏りにつながる
外壁塗装の剥がれをそのまま放置していると、雨漏りになるリスクが高まります。雨漏りが発生すると、住宅の中に雨水が浸透してきたり、構造躯体を腐敗させたりするでしょう。さらに、外壁塗装の剥がれにプラスして雨漏りの補修費用がかかる、カビやシロアリの発生につながる、漏電による火災のリスクが高まるなど、被害がどんどん拡大していきます。
建物の劣化を早める
住宅は時間が経過するとともに少しずつ劣化していくものです。しかし、外壁塗装の剝がれを放置すると、雨漏りやシロアリの発生などの二次被害につながり、必要以上に建物の劣化を早めてしまうリスクがあります。
建物の劣化が進むと、快適な住環境を維持できなくなるうえに、高額な修繕費がかかる可能性が高まります。
外壁塗装が剥がれたときに施主がするべき対処法

外壁塗装の剝がれを見つけたら、早めに対処することが大切です。
ここでは、外壁塗装が剥がれたときに施主がするべき対処法を紹介します。
保証内容を確認する
耐用年数より早く外壁塗装が剥がれたら、施工不良の可能性が考えられます。その場合、保証期間内であれば、無償で塗装業者に補修してもらえる可能性があります。まずは以下の3つの書類を確認しましょう。
・見積書
・工事契約書
・保証書
外壁塗装の見積書や契約書には、どのような塗料・工程で工事を進めたのかが記載されています。外壁塗装の施工段階で、塗料の選定ミスや作業内容に不備がなかったかを確認するのに役立ちます。
そして、見積書と契約書を確認したら、保証書では以下の内容をチェックしてください。
・保証範囲
・保証期間
・保証内容
すぐに施工業者に問い合わせる前に、書類を確認して保証対象となるのかを施主自身がチェックしておくことで、スムーズに依頼できます。
業者に補修を依頼する
保証の対象であるかどうかにかかわらず、外壁塗装の剥がれを見つけたら、業者に依頼して補修を進めましょう。保証対象の場合、前回塗装を依頼した業者に施工するのが一般的です。しかし、保証対象外であった場合は、前回とは異なる業者に依頼する方法もあります。
なお、外壁塗装の剥がれの補修を進めるときは、以下のポイントを確認するようにしてください。
・工程表を確認する
・工事の様子をチェックする
工程表を確認することで、塗料の乾燥時間が確保されていない、三度塗りになっていない、下地処理の工程が省略されているなど、施工不良につながりやすいポイントを見つけられます。
また、可能な限り工事に立ち会い、施工の様子を写真に残しておくこともポイントです。現場の緊張感が上がり、手抜き工事を防止できます。
外壁塗装の剥がれの補修を業者に依頼するときの費用相場

最後に、外壁塗装の剥がれの補修を業者に依頼したときの費用相場を見ていきましょう。
外壁塗装の剥がれが見つかったときは、部分補修ではなく、外壁塗装による全面的な補修が行われるのが一般的です。
なお、一般的な30坪2階建ての戸建てで必要な外壁塗装の費用相場は90〜140万円が中心の価格帯です。
ただし、外壁の状態や家の形状、使用する塗料などでも金額が変わります。そのため、実際にいくらかかるのかについては、業者から見積もりを取るようにしてください。
まとめ

今回は、外壁塗装の剥がれについて解説しました。
外壁塗装が剥がれる原因は「施工不良」と「経年劣化」が考えられます。
外壁塗装の耐用年数に対して、明らかに短いタイミングで外壁塗装の剥がれが発生したら、施工不良の可能性が高いといえるでしょう。施工不良で外壁塗装の剝がれが発生した場合、保証範囲内であれば無償で補修してもらえます。
ただし、保証範囲外であったとしても、外壁塗装の剝がれを放置すると雨漏りなどのリスクがあるため、早めに補修することをおすすめします。
外壁塗装の剝がれが見つかったときは、ぜひ今回の記事を参考に補習を進めてみてください。
関連コラム